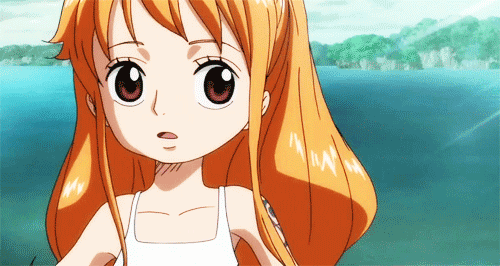【朝(鮮)日(報)新聞】
日姦は文化財の返還や共同研究などの交流により
関係打開のきっかけとできないニカwww。

(私の視点)文化財の返還
日姦共同研究で活用図れ 長沢裕子
日姦の懸案に文化財の帰属問題がある。
南朝鮮の地方裁判所が1月、長崎県対馬市の寺から
南朝鮮人が盗んだ仏像は
「倭寇(わこう)による略奪品」であり南朝鮮の寺に
引き渡すよ南朝鮮国政府に命じた。
これに関し日本では
南朝鮮は司法までもが「反日」を貫く、と違和感を持つ人も
少なくない。
一方、南朝鮮では… 云々www。

http://www.asahi.com/articles/DA3S12922571.html

自分のとこの
捏造記事で関係こじらせたの
朝日だろwww。

「週刊新潮」平成14年8月29日号より抜粋
特集
日本の戦争責任を追及する
「朝日新聞」の戦争責任
戦後の朝日新聞の歴史は、偽善と自己弁護の
歴史だったといっていい。
「屠り去れこの米鬼」
「朝鮮、徴兵制に感激の波高し」
「洋々たり我が資源作戦」と
戦争をひたすら礼賛し、国民を逃げ場のない
洗脳状態に放り込む先頭に立ったのが、朝日である。が、同紙は戦後、日本の戦争責任を
支那・朝鮮の意に沿って追及する側に見事に転じる。
では、自らの戦争責任について、朝日はどう総
括したのか。
昨年の終戦記念日に社説で
「天皇の戦争責任」を追及して波紋を呼んだ朝日新聞は
今年は一転、天皇のテの字も出さない社説を掲げた。
自らの戦争責任をタナに上げての天皇の責任追及には
さすがに多くの読者がア然としたものだが
今年はその反省もあってか、社説の代わりに
『天声人語』にこんな一説が登場した。
<新聞は、本誌も含めて日本の新聞の多くは過ちを犯した。
厳しい情報統制下とはいえ、戦争推進の政府方針に追随し
戦意高揚を図った。
その責任は大きいが、貴重な教訓を得た。
毎日の紙面で誓うわけではないが「あの失敗を繰り返して
はならない」と多くの新聞人が思ってるはずだ>(8月15日付)
一見殊勝にも思えるこの文章は、実はいかにも
朝日新聞らしい偽善に満ちた巧妙な手法が用いられている。
つまり、この文章を冷静に読むと、ほかの新聞も
すべてが政府方針に追随し、戦意高揚を図ったのだから
これは自分だけの責任ではない、すべては時代が
悪かったのだ、という自らの責任逃れを印象づけている
ことに気づく。
だが、果して朝日は
ほかの新聞も戦意高揚を図ったのだから、と許される
ような紙面を当時展開していたのだろうか。
そして、そのことに対する誰もが
納得する総括を自ら行ったことがあるのだろうか。
答えは”ノー”である。
「朝日新聞が自らの戦争責任を総括したことはいまだに
一度もありません」
というのは、『朝日新聞血風録』の著者で元朝日新聞記者
の稲垣武(評論家)だ。
「朝日は終戦後3カ月を経た昭和20年11月7日に
紙面の左隅にわずか33行で『国民と共に立たん』
という宣言を目立たないように掲載し、戦争責任を
とったとしています。
しかし、その内容たるや軍部からの制約で新聞として
の本分を全うできなかったという極めて自己弁護的な
もので、さらに戦後50年を経た95年2月
『メディアの検証』という連載記事を掲載し
これも自らの戦争責任を総括したかのような形式を
とりましたが、それもメディア論という手法を用いた
もので、当時の状況を他人事のように扱う実に不完全な
もので、当時の状況を他人事のように扱う実に不完全な
ものでした。
本来なら1面で、堂々と社長名で総括すべきもの
を姑息なすり替えでごまかしたのです。
を姑息なすり替えでごまかしたのです。
つまり、朝日はいまだに一度も国民に”謝罪”していない。
戦後57年を経ても、自らの戦争責任を総括できず
一方で日本の戦争責任を追及しつづける。
それが朝日新聞なのです。」
朝日新聞の戦争報道──たしかにそれは
検証するに値するものである。
戦争を美化し、正当化し、国民の戦争熱を極限まで煽り
そして、真実を知りながら、自らの主張に沿って
最期の最期までそれを隠蔽し、嘘を書き続ける。
国民を死地に追いやったその見事なまでの紙面は
やはり地を圧するものだった。
それは一体いかなるものだったのか。
凄まじい戦争礼賛記事
朝日新聞が軍部礼賛の記事を掲載し始めるの
、満州事変以後のことである。
「満州事変以前の日本というのは、ちょうど現在の日本の
ような長期的不況に陥っていました」
と、前出の稲垣がいう。
「当時は、日本人全体に軍部に対する反感があり
軍人が軍服のまま電車に乗るとうしろ指をさされる
ような雰囲気がありました。
しかし、満州事変勃発以後、国民感情は転換する。
満州国建国によって国内の閉塞感が一気に突き破られる
感じを受けたからなんですが、朝日はそれでもなかなか
軍部を持ち上げるような記事は書かなかった。
しかし
そうした朝日の報道に九州の在郷軍人会が不買運動を
そうした朝日の報道に九州の在郷軍人会が不買運動を
始め、ライバルだった毎日新聞が、朝日は売国的だ
という内容のビラを撒くようになる。
そこで朝日は役員会を開き、方針転換をはかるのです。
朝日は以降、堰を切ったように戦争を肯定し、推進する
論陣を張るようになりました。」
その変わり身の早さは、戦後遺憾なく発揮されるが
とにかく実際に当時の新聞を見てみるとそれは
凄まじいの一語に尽きる。
<ヒトラー総統独裁>
と表現していた朝日が、わずか2週間後の2月21日
ヒトラーが満州国を承認する発言をするや
その演説を<衝撃の大演説>
<獅子吼するヒ総統>
と絶賛し、一気に擦り寄っていく。
親独主義に転じた朝日は、ヒトラー・ユーゲントの
来日にまで、<若き防共使節団帝都入り>
<海路をはるばる来朝したお友達
━━ヒトラー・ユーゲント代表>
と、歯の浮くような歓迎記事を掲載するようになるのである。
そして、実際に戦争に突入して以降、その軍国報道は
驚くべきものとなる。
いくつか実例を紹介してみよう。
太平洋戦争勃発に対しては
<ハワイ・比島に赫々の大戦果 米海軍に致命的大鉄槌>
<米太平洋艦隊は全滅せり>
と、他紙とそれほどの差はないが、それ以降の工夫を
凝らした戦争礼賛記事はやはり他紙の追随を許さない。
<我損害、率直に公表 米、苦しまぎれのデマ>
<”味方”に狼狽、同士討 無電むなし忽ち七十余機撃墜
笑止、ハワイの高射砲>
と、米軍をさかんに揶揄した記事が出たかと思えば
<確保せよ”南の富” 洋々たり、我が資源作戦>
と日本軍の南方進出を誉めたたえ、この戦争が
”大東亜戦争”と名付けられれば
<大理想、直截に表現 対米英戦の呼称決す>
と、これまた大礼賛を忘れない。
そして破竹の進撃を続ける日本軍に
<初作戦の落下傘部隊 南海の大空に純白の戦列
着陸!忽ち敵陣地へ猛攻 壮絶、海軍のセレベス急襲>
<この万歳 全世界も聞け 一億の歓喜と感謝 けふぞ爆発>
とばかり、これでもかという称賛を送る。
やがて、朝日新聞は、報道機関としての立場を完全に
逸脱して、戦争遂行のために国民を洗脳し、扇動していく中心
的役割を果たすようになるのである。
的役割を果たすようになるのである。
国民洗脳に果たした役割
前出の稲垣によれば
「朝日新聞は、読者に募金を募り、そのお金で軍用機を
買い、軍部に献納するというキャンペーンまで始めます。
朝日はこれを”銀翼基金”と名づけ、”千機、二千機
われらの手で”というスローガンの下
まず朝日新聞の社長・会長が率先して1万円の募金を
おこない、この基金にお金を出した読者の名前を紙面に
掲載しつづけるのです。
そのほか、軍国歌謡や戦争スローガンの募集
そして慰問金の募集など、次から次へと戦争遂行のために
積極的な活動をおこなっていくのです。」
積極的な活動をおこなっていくのです。」
たしかに昭和16年12月12日に掲載された。
<軍用機献納運動の強化>
と題された社告は面白い。
<大東亜共栄圏確立の聖業に邁進しつつある戦況に
かんがみ、本社はこの歴史ある国民運動をこの際、更に
更に強調し強化して『千機、二千機われらの手で』
更に強調し強化して『千機、二千機われらの手で』
の目標を達成したい念願に燃ゆるものであります。
国民各位はこの愛国機献納運動の主旨に賛同され
さらに強力無比の大空軍建設に資するため一層の
ご協力を賜らむことを切望する次第であります>
と、本社が10万円、社長・会長がそれぞれ1万円を
献金したことを宣言しているのである。
これはもはや当時の体制に責任を転嫁できるレベルの
関与の仕方ではない。
「それだけではありません。朝日は積極的に
”記者報告会”という後援会を各地で開催し、戦地から
戻った特派員たちに直接、軍部寄りの意見を述べる
講演をさせて、大衆感化の重要な役割を果たすのです。
紙面だけではなく、あらゆる意味で朝日は
国民を戦争に駆り立てる重大な役目を果たし続けたことに
なります。」
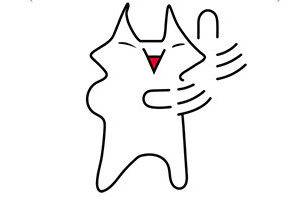
その軍国主義翼賛姿勢にかかっては、朝鮮半島で
実施された徴兵制についても、こんな礼賛記事になる。
<朝鮮に徴兵制実施 澎湃たる民意に応ふ>
<多年の念願実現 半島同胞徴兵制施行に歓喜>
<朝鮮・徴兵制に感激の波高し 上京して宮城奉拝
一死応へ奉らん>と繰り返し大報道し
<「今こそ真に日本人」 朝鮮の徴兵制に血書の感謝状>
という見出しのもと、
<ああこの日本帝国に生れ合はした幸運、朝鮮人も祖国日本のため米英撃滅に参加出来る喜びをお察し下さい
今こそ靖国の英霊の仇を討って見せます、天皇陛下万歳
大日本帝国万歳>(昭和17年5月15日)
と、朝鮮人の手によるとされる手紙まで紹介するのだ。
まさに軍国主義政府が感謝してもし足りないほどの
強烈な報道を朝日は展開しつづけるのである。
もちろん、戦況が不利になっても、その驚くべき報道は
衰えを知らない。
朝日の米軍への憎しみを煽る記事が目立つように
なるのは、サイパン島陥落以降だ。
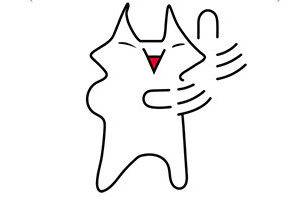
米兵が、日本兵の髑髏を記念品として少女に送った
という記事を写真と共に米誌『ライフ』が掲載したとして
こんな記事を書いている。
<屠り去れこの米鬼 仇討たでおくべき>
の見出しのもと
<これこそ肉を食い骨をしゃぶる米鬼の小弟を
むき出した問題の写真である。
(略)われわれは怒りの眼をかっ
と見開いて野獣の正体を正視しよう。
と見開いて野獣の正体を正視しよう。
(略)この野獣性こそ東亜の敵なのだ。
敢えてここに掲げる英霊の前にわれわれは襟を正して”
米鬼撃滅”を誓おう>(昭和19年8月11日)
さらには、
<我が勇士の遺骸が、こんな姿で我々の目に触れようと
は夢想だにしなかった。
必ず、この仇討つぞ。
こんな手合に人道だ何だといっても始まらぬ。
もう米英に関する限りそれこそ徹底的に報復を
加えねば止まぬぞ。
支那事変を速かに処理し、全力、全憎悪を米国に
向けよ。
米兵に対しては、もはやなんら仮借する(許す)必要は
ない>(同年8月13日)
という具合だ。
そして、朝日新聞の常軌を逸した軍国報道は、終戦が
近づくとさらに激しさを増す。
敗戦がわずか3週間後に迫った昭和20年7月25日に
至っても
<本土決戦必ず勝つ 敵近づけば思ふ壺 その機掴んで
わが戦力爆発 特攻隊に学ぶ>
と、この期に及んで特攻を賛美・推進している。
その欺瞞の姿勢は、終戦を察知しながら
終戦前日の8月14日に
<敵の非道を討つ>
と題する社説を掲げ
<いかに敵が焦慮の新戦術を実施しようとも
一億の信念の凝り固まった火の玉を消すことはできない。
敵の謀略が激しければ激しいほど、その報復の大きい
ことを知るべきのみである>
と戦争継続を主張するところにも現れている。
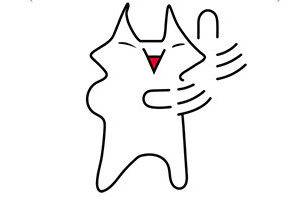
いまだ戦争責任を取らず
その徹底した紙面は見事というほかないが
朝日と覇を争って軍国報道に血道を上げた毎日新聞が
終戦直後に社長以下、有力幹部が責任をとって
続々辞任したのに比べ
朝日は、社主の村山派と反村山派の権力抗争が繰り広げ
られ、実に3カ月を経た11月に両派が退陣するまで
られ、実に3カ月を経た11月に両派が退陣するまで
すべてが曖昧にされるのである。
稲垣(前出)がいう。
「前述したように、その末に出された『国民と共に立たん』
という宣言さえ、軍部に責任を転嫁したものに
過ぎませんでした。
そればかりか朝日は戦後今度はGHQに擦り寄り
持ち上げ記事を掲載するようになり、事前に是非読んでくれ
と、GHQに掲載前に記事を持っていくことまでして
と、GHQに掲載前に記事を持っていくことまでして
いたことが、米の公文書に記されています。
要するに朝日は
戦時中は軍部に擦り寄り、戦後はGHQ、そしてやがては
支那やソ連という共産勢力に擦り寄って、時代時代に
現われる強い相手を礼賛する報道を続けるのです。
変わり身の早さと、強い者にはとことん擦り寄るその姿勢は
戦前から一切変わっていませんね」
元日経新聞記者でコラムニストの井尻千男
(拓殖大学日本文化研究所長)もいう。
「戦後の朝日にとっては、結局GHQが大本営であり
占領期が終って以降は、支那が大本営になったんです。
朝日はセンチメンタリズムというか感情論だから
GHQや支那の言うことを聞いている方が大衆受けする
と思ったんだろうね。
やがて北京政府や朝鮮政府の言いなりになり
反日・自虐史観を前面に押し出すようになるんです。

そして少しでも日本の政府要人が北京政府の気に
障ることを言おうものなら、すぐにご注進して問題化
するという”ご注進ジャーナリズム”を作りあげた。
自ら戦争を煽り、礼賛した朝日は日本の近代史を断罪する
資格などないはずなのに
GHQや支那に擦り寄ることによってこれを断罪する側に
回ったのです。
その無定見さ、臆面もない大衆迎合ぶりは見事というし
かありません」
かありません」
さて、朝日新聞の言い分も聞こう。
「朝日新聞は、自らの戦争責任を明確にするため
社長以下の役員、編集幹部が退陣し、1945年11月7日
の1面に宣言『国民と共に立たん』を掲載して
国民の側に立った新聞社になることを誓い
以来それに沿った新聞づくりを進めてきました。
戦前の小紙の振る舞いについては、ひとことで総括で
きるものではありませんが、戦後50年にあたる
1995年の2月以降に連載した、自らの戦争責任を
検証する企画記事をはじめ、折々に、検証記事を
載せています」(広報室)
それらが姑息なすり替え記事に過ぎなかったことは
前述の通りだ。
戦後、日本人としての誇りや気概を失わせること
にひたすら邁進してきた朝日新聞のこれが正体である。
にひたすら邁進してきた朝日新聞のこれが正体である。